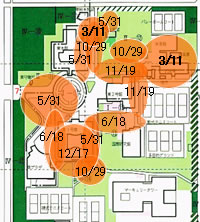「一橋大学とイチョウ その1」一橋大学名誉教授 田﨑 宣義
「一橋大学とイチョウ」問題は一橋大学入学以来の謎のひとつで、いまもって謎の状態が続いている。もっとも中味は多少変化して、「あるいは…」という地点までたどり着けたか、という気もしないではない。以下はその現況報告なので、調べ足りない箇所が多々あることをお詫びしておかなければいけない。
*
まずは、私の「一橋大学とイチョウ」問題とはなにか、を説明することから始めたい。
私がこの問題に最初に遭遇したのは入学式であった。新入生に配られた「一橋の歌(武蔵野深き)」の歌詞カードに「銀杏会同人作詞、山田耕筰作曲」とあるのを見つけた時である。ただしごく最近になって「ぎんなん会同人」と読むと大澤俊夫先輩から教えて頂いた。私は「銀杏」をイチョウと読んでいたので、使い分けが新しい謎になったが、まだ手がかりがつかめていない。
また毎日通う大学通りには桜とイチョウが交互に植えられている。このうち、桜は今上天皇誕生の記念植樹とわかったが、なぜイチョウが植えてあるのかは謎のままである。
さらに東西の両キャンパスとも、正門をくぐるとイチョウが出迎える。一部がやや密植気味だが、なぜイチョウが出迎えるキャンパスに仕立ててあるのか。
こう見てくると、一橋大学とイチョウには繋がりがありそうなのだが、それが判らない。これが、私の「一橋大学とイチョウ」問題である。


*
ところが最近になって、一橋大学とイチョウの繋がりが神田一ツ橋時代にあることが分かってきた。
たとえば、昨年創立100周年をむかえた一橋消費組合の襟章は、イチョウの葉に「CO-OP」の文字をあしらっている。同じイチョウの葉をアレンジした東京都のマークも東大の校章も、制定は戦後である。一橋消費組合のイチョウの方が遙かに歴史が古い。
イチョウは歌にも登場する。いまでもよく歌われる「一橋の歌(空高く)」の冒頭も、次のようにイチョウで一ツ橋の母校を象徴させている。
空たかく光みなぎり 照り映えてさゆらぐ公孫樹
白雲の湧きたつところ そここそは輝く聖地
これぞこれわが母校 懐かしのふるさと
その名讃えてこゝに集ひつ その名さゝげて永久に変わらじ
あゝ一ツ橋われらが母校
当時は「照り映えてさゆらぐ公孫樹」と歌うだけで、神田一ツ橋のキャンパスと学園生活を彷彿とさせたにちがいない。そう思わせる歌詞である。
ちなみにこの歌は酒井敬三郎作詞、山田耕筰作曲で、大学本科が国立に移転する1930年に歌詞を公募して作られた。公募したのは「全一橋同人の歌である。商科大学学歌でもあり、一橋会会歌でもあり、又如水会会歌でもある」全一橋人の歌で、一橋会と如水会の連名で募集のよびかけが行われた。
当選したのは、一ツ橋への惜別の歌であったが、冒頭からイチョウが歌われているところに、イチョウと一ツ橋との並々ならぬ繋がりを感じさせる。翌年の籠城事件で愛唱され、創立75周年の1950年に「武蔵野深き」が生まれるまでは唯一の「一橋の歌」であった。
一橋消費組合の襟章と「空高く」から、母校とイチョウは神田一ツ橋時代から深いつながりのあったことが分かるが、さらに遡って明治37年にできた「一橋会歌(長煙遠く)」にも、次のようにイチョウが登場する。
あゝ一ツ橋空高き 母校の春の朝ぼらけ
銀杏の梢青葉して 若き光の冴える時
梧桐の影に語らひし その歓楽のあとかたや
『一橋歌集』第26版を開くと、ほかにもイチョウの登場する歌がある。大正10年の予科の歌「見よ七彩の」と専門部会々歌「鱗雲なびき」、翌年の予科の歌「夜の香こむる」、大正13年の専門部会々歌「更けゆく秋の」、昭和9年の予科会々歌「緑にかざす」などである。「鱗雲なびき」の歌詞「銀杏の梢かゞやきし 諸葉は鐘に散り敷くよ」は一ツ橋キャンパスの光景を彷彿とさせる。また「見よ七彩の」と「更けゆく秋の」の歌詞には「聖樹」という言葉がある。この「聖樹」はイチョウを指すのだが、このことは後で触れる。
この5曲のうち、「緑にかざす」は作詞が北原白秋、作曲山田耕筰で、この歌ができた昭和9年は予科の小平移転の翌年だが、他の4曲はいずれも一ツ橋時代のもので、ここからも、一ツ橋とイチョウの繋がりの強さがわかる。
*
しかもこの一ツ橋時代のイチョウは、イチョウ一般、つまり普通名詞のイチョウではなく、「聖樹」、つまり固有名詞の、あるいは定冠詞つきのザ・イチョウなのである。このことに気づいたのは、一ツ橋時代の卒業アルバムを繰っていた時である。
明治43年以降のアルバムには、必ずといってよいほど1本のイチョウの写真が登場する。写真のキャプションはただ単に「公孫樹」とするものが多いが、中には「聖樹」とか「聖樹 公孫樹」などもある。管見の限りだが、「公孫樹」が「聖樹」となるのは大正の半ば以降のようである。管見の限りだが、イチョウ以外の「聖樹」にはお目にかかっていない。
「聖樹」は、昭和になって国立に移転した後にも、登場する。
昭和13年の本科卒業アルバムには、「人々より聖樹として敬愛せられし公孫樹」というキャプションで神田一ツ橋のイチョウの写真が登場する。もちろん1本のイチョウである。翌年の本科卒業アルバムには、母校の歩みの項に「そして遂に大正九年四月、春光燦々と注ぐ中一橋々畔に東京商科大学の門柱は高々と掲げられた。一橋同人聖樹公孫樹を囲つて狂喜乱舞、何時果てるとも知れなかつた。一橋三十年の宿望は達せられた。想へば永い苦闘であつた」という下りがある。
神田一ツ橋時代の本学とイチョウの関係は、国立移転後にも続くのである。
もちろん、一ツ橋キャンパスのイチョウは1本だけではない。大正6年竣工の御大典記念図書館の脇にもイチョウがある。にもかかわらず、ザ・イチョウは1本である。
では、ザ・イチョウは、どんなイチョウだったのか。


*
この謎は、清水都代三『一橋挿話』(東亜堂書房、大正6年)に収められている「公孫樹縁起」の冒頭の一文で解けた、と思っている。著者の清水氏は大正6年春の東京高商本科卒で、『一橋挿話』は三井物産神戸支店赴任中に出版されている。この本には、1本の大イチョウと根本のベンチでくつろぐ学生の描かれた口絵がある。冒頭の一文を掲げよう。
空を衝きつつわしや何処までも
伸びて茂つて秋や散りこぼれ
枯れて掃かれて焚かりよとまゝよ
幹は三抱へ背丈は九丈
空をつき衝きわしや育つ……
正門を入つて、右へ十二三間が程に立つてゐるのがそれだ……
ザ・イチョウは、正門を入って右の方に天を衝いて立っていた。口絵とこの一文からも、「わし」とよばれるイチョウは1本と考えてよいだろう。「幹は三抱へ背丈は九丈」はまさに大銀杏である。口調のよさに任せた表現かも知れないが、福羅先生の回想にも「都内では珍しい公孫樹」(『国立・あの頃』)とある。
さらに清水氏は「公孫樹(こうそんじゅ)は一橋(いつけう)の神様である。少なくともあの校庭にそゝり立つ公孫樹を、一種崇高(サブライム)なものとして眺めたい……」、「何処の学校にだつても、その学校を表象化(シムボライズ)するものがあるものだが、一橋ではこの公孫樹を、下らなく因縁づけずに、無意味に、たゞ漠然とその偉大なる存在に支配されて、一にも二にも渇仰する」(ルビは原文)と書いている。
ザ・イチョウは一橋の神様、そそり立つ姿は崇高で、学園の象徴、橋人の渇仰の的だ、という。一橋とイチョウの繋がりの強さは格別である。さらに次のようにも書いている。
……一日二日と見慣れるに従つて、何処の大木よりも、この公孫樹が懐かしくなるから先づ不思議である。確かに公孫樹は一種の魔力を持つてゐる。魔力を持つてゐると謂つたつて、なにも植物学(ボタニイ)が断定した生存力と伸長力の範疇を出ないのだが、――兎に角、一橋の学生はこの老木を一種の記念塔にしてゐる。一橋に学んでゐるうちは、さして気にも留めないやうだけれど、遠く異境に故国を想ひ、かくて一橋を懐(おも)ふ時、思慕の情は先づこの老木に髣髴として立ち帰るそうな。
時を違へず季節は廻る、散り去り生ひ茂つて幾星霜、落葉(おちば)は積んで焚き捨てられるまでも、巍然として冬空(とうくう)に屹立してゐる姿は、そのまゝに一橋の宗教である。理窟ではない感じである。
ザ・イチョウの明治30年代は、内藤章先生の回想談に「僕等の学生時代には校門は今よりもつと右よりにあつて、校門を入ると銀杏の木陰の下に芝生が茂つてゐて昼の休みなんかにはそこへ学生が集まつて」(『一橋新聞』昭和5年8月25日付)と登場する。
これらを読むと、「一橋会歌(長煙遠く)」、「一橋の歌(空高く)」などに登場するイチョウも、「記念塔」の「老木」ザ・イチョウを歌っているように思えてくる。
また一橋消費組合の襟章も、ザ・イチョウと「CO-OP」の文字で、一橋・消費組合を意味していたのだろう。
*
こうして、一ツ橋時代の母校とイチョウとの関係がいかに緊密だったかは見えてきたように思うのだが、いかがであろうか。
やがて震災があり、国立移転の時を迎える。移転は一ツ橋との別れであり、このイチョウとの別れでもあった。その別れがどのように国立のイチョウにつながるか等々は、想像の域を未だに出ないのだが、次の機会に述べることにしたい。